ザルツブルク、宮廷オルガニスト、モーツァルトのありのまま! [2006]

映画『アマデウス』に登場するサリエリは、モーツァルトへの妬み、嫉みを内に抱える、何とも言い難いライヴァルとして登場する。その何とも言い難いドス黒さのようなものが、サリエリ=悪役像を増幅させてしまったか?一方で、より解り易く悪役として描かれていたのが、ザルツブルク大司教、コロレド伯、ヒエロニュムス。モーツァルトがその才能を発揮しようとすると、邪魔をして来る意地悪な存在... なのだけれど、改めて、この人物に注目してみると、また違ったイメージが見えて来る。例えば、見事にヴァイオリンを弾いたとか、宮廷劇場を創設したとか、よくよく丁寧に見つめると、モーツァルトに対しても、けして邪険に扱ってはいなかった(一度、離職したモーツァルトが、再就職を願った時には、以前の3倍の年俸で迎え入れた!)とか... ザルツブルク大司教の宮廷よりも、より大きな宮廷にポストが欲しい!あるいは、フリーランスとして活躍したい!というモーツァルトの視点に立つと、随分とブラックな雇い主のように映るものの、けして悪い君主ではなかったことが窺える。というより、啓蒙主義に傾倒し、聖界諸侯でありながら、より近代的で世俗的な統治を志した異例の人物だった。
そんな大司教について、ザルツブルクについて、少し詳しく見つめながら、大司教の宮廷楽士長、ミヒャエル・ハイドンの教会音楽集に続いての、大司教の宮廷オルガニスト、モーツァルトによる教会のための音楽に注目... マルティン・ハーゼルベック率いる、ウィーン・アカデミー管弦楽団の演奏で、モーツァルトの教会ソナタ全集(CAPRICCIO/C 71064)を聴く。
コンチェルトという劇場、パガニーニ、シュポーアによる華麗なる舞台。 [2006]

スタンダール曰く、ナポレオンが去って、ロッシーニがやって来た。そう、ロッシーニの時代というのは、ポスト・ナポレオンの時代となる。それは、ナポレオンが引っ掻き回したヨーロッパを、如何に元の状態に戻すかを話し合ったウィーン会議により形作られた、ウィーン体制、保守反動の時代。そうした時代に、巨匠、ベートーヴェンは悩まされ、新世代、ロッシーニは波に乗った。キラキラと弾けるブッファ、格調高くも華麗なるセリア... ロッシーニのオペラを改めて振り返ると、アンシャン・レジームに一世を風靡したナポリ楽派の記憶が最上の形で響き出すように感じる。そのあたりが、過去を顧みる時代の気分にぴったりだったのだろう。しかし、革命と戦争を経て再現される過去は、フェイクに過ぎない... ポスト・ナポレオンの時代というのは、どこか禍々しく、現実逃避的で、独特な軽薄さが漂う。そのあたりを象徴するのが、ヴィルトゥオーゾたちの音楽なのかもしれない...
ということで、ポスト・ナポレオンの時代に活躍した2人のヴィルトゥオーゾに注目。ヒラリー・ハーンのヴァイオリン、大植英次の指揮、スウェーデン放送交響楽団の演奏で、1811年に作曲された、パガニーニの1番のヴァイオリン協奏曲と、1816年に作曲された、シュポーアの8番のヴァイオリン協奏曲、「劇唱の形式で」(Deutsche Grammophon/477 6232)を聴く。
弦楽四重奏というプリズムが響かせる、北欧の内なる声。 [2006]

今年、フィンランドは、独立100周年を迎える。ヨーロッパというと、歴史が古いイメージがあるのだけれど、国家としては、意外と新しいところが多い。そして、北欧では、ノルウェーもまた新しい(中世末までは独立国だったので、「新しい」とは、ちょっと違うか?)。フィンランドがロシアから独立(1917)する12年前、1905年、ノルウェーはスウェーデンから分離している。となると、北欧のお馴染みの作曲家たち、ノルウェーのグリーグ(1843-1907)、デンマークのニールセン(1865-1931)、フィンランドのシベリウス(1865-1957)が生まれた頃の北欧の地図は、今とまったく異なるわけだ(ま、北欧に限らずなのだけれど... )。100年遡るだけで、今とは違う世界が広がるという事実を前にすると、アメリカの新大統領も、ハード・ブレグジットも、壮大なる変奏曲である歴史の一端に過ぎないことを思い知らされる。いや、そういう、大きなスパンで世界を見つめることが、今、とても必要な気がする。物事は変わることを前提に見据えなくてはいけない。ふと、そんなことを思う、今日この頃...
さて、北欧です。シベリウスの交響曲に続き、北欧のお馴染みの作曲家たちにも目を向けまして、エマーソン弦楽四重奏団による、グリーグの弦楽四重奏曲、ニールセンの「若い芸術家の棺の傍らで」、シベリウスの弦楽四重奏曲、「内なる声」という、北欧の弦楽四重奏のための作品を集めた"INTIMATE VOICES"(Deutsche Grammophon/477 5960)を聴く。
モーツァルトの青春、古典主義の陽春、交響曲の新緑。 [2006]

アーノンクールのマタイ受難曲を聴いて、ブーレーズのメシアンを聴いて、2人のマエストロをしのんでの、ちょっと取って付けたようだけれど、ブーレーズ、アーノンクールを、今、一度、聴いてみたいなと... やっぱり、この2人は、20世紀後半のクラシックの最後を象徴するキーパーソンだったと改めて感じて。本来、保守本流に、もの凄く挑戦的な態度で向き合っていたはずが、保守本流の弱体化によって、その命脈を保つための新しき血として迎え入れられ、やがてクラシックの大家になってしまうという、特異な存在。裏を返せば、クラシック衰退を象徴する存在でもあったのかもしれない。この2人が、クラシックというスノッブな世界で活躍することは、とても痛快な一方で、大家となってしまったことには、少し複雑な思いも... が、衰退してクラシックは、一皮剥けて、おもしろくなったのかもしれない。この2人が大家に押し上げられるという大逆転こそ、クラシックの可能性!
ということで、今回は、春らしく?モーツァルトを... ニコラウス・アーノンクールが率いた、ウィーン・コツェントゥス・ムジクスの演奏で、10代後半のモーツァルトを追う、初期交響曲集 Vol.2(deutsche harmonia mundi/82876757352)を聴く。
フランスの外から「フランス」を捉える... マスネ、フランク... [2006]

最近、神社の本をいくつか読む。で、神社について知らないことがいっぱいあることを思い知らされる。一方で、日本の神様について、実は、よくわかっていないことも多いらしいことを知る。つまり、本当の意味での日本のオリジナルとはどんなものだったか?記紀は多分に編集されているようだし、仏教ともハイブリットな期間が長かったわけだし、それをまた近代日本が強引にひっぺがしたことで、余計にオリジナルから遠くなったようなところもあるようだし、結局、オリジナルなんてものは幻想に過ぎないのかもしれない。裏を返せば、様々に外からの影響を受け歩んで来た道程こそが"オリジナル"と言えるのかも... 変容してゆく姿こそが、日本のオリジナル... それは一言で語り切れるような代物ではなく、安易に「日本的」なんて、ひとつのイメージで括ることはできない。
さて、この春、フランスを巡って来たのだけれど、フランスもまた、ひとつのイメージで括ることのできない国... 思いの外、ドイツ的でもあったシャブリエの音楽を聴いて、ふとそんなことを考えてしまう。そしてまたさらに、「フランス」というイメージを越えてゆく音楽を聴いてみようかなと... トルコのピアニスト、イディル・ビレットと、アラン・パリスの指揮、トルコのオーケストラ、ビルケント交響楽団の演奏で、マスネとフランクのピアノのための協奏的作品集(Alpha/Alpha 104)を聴く。
テクノ・パレード! [2006]


12月に入って、何となくフランスの音楽が続きます。
と言っても、少し外しての「フランス」なのだけれど... で、タローのキャバレーに、ジェロルスタン女大公殿下と、多少、裏通り系なチョイス?けれど、「フランス」というだけで、何かキラキラとした華やぎがある。それは、「ドイツ」では味わえない軽やかな輝きで、何となく今頃の街並みの、電気でキラキラとしているのに似ている?というフランスの音楽の、現代音楽を聴いてみるのだけれど、やっぱりキラキラがあるからおもしろい。
ということで、ポスト・ミニマルなフランスの現代の作曲家、ギヨーム・コネソンの、ポップな室内楽作品を集めた1枚... エリック・ル・サージュのピアノを中心に、フルートのマチュー・デュフォー、クラリネットのポール・メイエら、何気に豪華なフランスのマエストロたちが顔を揃えての、2006年にリリースされたアルバム、"techno parade"(RCA RED SEAL/82876 662722)を聴く。
ビザンティウムから、アンダルシアへ... 時代と国境を越える旅。 [2006]
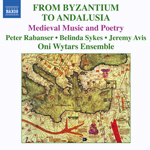

大西洋を旅して来たので、少し気分を変えて地中海へ...
ところで、近頃、この地中海が騒がしい。北岸では経済が、南岸では宗教が、火を吹いている。そうしたニュースばかりを見せられると、地中海は随分と物騒な海に思えてくる。が、様々な文明が行き交い、豊かな文化を生み出したのもまた地中海。衝突すら新たな潮流につなげてしまう、懐の深さを示してきたその歴史を振り返ると、他の海にはない密度があって、圧倒されてしまう。何より、地中海を取り囲む文化の多様性!そうした数々の文化が< 荒波に揉まれて織り成した地中海文化圏に、底知れぬものを感じてしまう。
という地中海の中世に遡り、ビザンティウムからアンダルシアへと旅する、圧巻のライヴ!2006年にリリースされた、気鋭の古楽アンサンブル、オーニ・ヴィータルスによる、"FROM BYZANTIUM TO ANDALUSIA"(NAXOS/8.557637)を聴き直す。
ラルペッジャータの、ミッション、インポシブレス。 [2006]

"Los Pajaros Perdidos"、"Bolivian Baroque"と、ラテン・アメリカが続きます...
クラシックにとってもの凄く遠い場所のようでいて、意外と密に歩んで来たラテン・アメリカとヨーロッパ。ピアソラがパリでナディア・ブーランジェに学んだばかりでなく、もっともっと時代を遡って、バロックの頃、今からすると意外なほど盛んに交流していた史実。ヨーロッパの音楽がラテン・アメリカに持ち込まれ、ラテン・アメリカの土着の文化が融け込み、それがまたヨーロッパに持ち込まれ、一大ブームを呼んだり。クラシックのステレオタイプを、一枚、剥がすと、より刺激的な音楽史の姿が現れる。特に、バロック期のラテン・アメリカとヨーロッパの間には、ラテン・ミュージックの先祖とも言うべき、異文化が共鳴し合って生まれる魅惑的な音楽がすでに存在していた。
そうしたあたりを、よりイマジネーションを膨らませて綴ったアルバム。2006年にリリースされた、クリスティーナ・プルハル率いるラルペッジャータ、そしてキングズ・シンガーズらを招いての刺激的な1枚、"Los Impossibles"(naïve/V 5055)を聴き直す。
ボリビアにて、バロックの素朴... [2006]

音楽は国境を越える!
一方で、台湾のオーケストラの中国公演で、日本人メンバーのビザが下りなかったというニュースを耳にしたりする。で、虚しくなる。音楽は国境越える... なんてことを発言するのは、今や無邪気過ぎるのかもしれない。何だかわけもわからず、次から次へと押し寄せていたK-POPも、今となっては手のひらを返したような印象すらある。音楽は国境を越える、と思いたい。が、一方で、音楽を創り出す"人間"というのは、つくづく愚かなのだなと感じる21世紀。そして、やたら愚かさばかりが目につく今日この頃でもあって。ひとつ気分を変えるために、バロック期、国境どころか海すら渡った音楽を聴いてみようかなと... それは、ヨーロッパからボリビアへの旅...
思い掛けなくたくさんのバロック期の楽譜が発見された、ボリビアのコンセプシオン伝道所。南米の奥深く、タイムカプセルの役割を担った教会で、かつての音楽を蘇らせようというプロジェクト、オランダのピリオド・アンサンブル、フロリレジウムによる、"Bolivian Baroque"のシリーズから、2006年にリリースされたvol.2(Channel Classics/CCS SA 24806)を聴き直す。
旅の手帖。 [2006]

さて、秋は旅行シーズン!とは言うものの、実はピンとこない...
夏のヴァカンスに、冬のスキー・リゾートなんて洒落込まなくとも、ゴールデン・ウィークに盆に正月と、旅行は季節を問わない。というより、秋こそ抜け落ちている?数年前には、シルバー・ウィークなんて、盛り上がったこともあったはずだが、どこかへ行ってしまった。となると、秋は旅行をしないシーズン?芸術の秋、読書の秋と、何となしに内に籠るのが秋の作法のようにも感じるのだけれど。ということで、内に籠って旅をする?
秋は音楽による旅行シーズン... 旅する音楽シリーズをやってみようかなと、ふと思い付く(いや、いつも"オモイツキ"なのだけれど... )。その第1回として、ルネサンスからバロックへと移ろう頃、イギリスからアラビアまでを旅したという、フランスの作曲家、テシエの音楽を聴く。それは、各地の音楽が詰まった旅の手帖。
2006年にリリースされた、ヴァンサン・デュメストル率いる、古楽アンサンブル、ル・ポエム・アルモニークによる、"Charnets de voyages"(Alpha/Alpha 100)を聴き直す。


