1920年代、籠められたエスプリ、伝統が深めるダーク... [before 2005]
1920年代のピアノ協奏曲のシリーズを聴いて、その時代の音楽を見渡して見ると、まったく以って興味深く、何よりおもしろいなと、つくづく感じる。様々な個性による多種多様な作品がおもしろいのは当然なのだけれど、その多種多様さを俯瞰した時に感じられる、まるでパーティーをしているかのような浮かれよう!そこには、第1次大戦の破壊により失墜した伝統からの解放もあったのだろうけれど、西洋音楽のプレイヤーが増えたことも大きかったように感じる。ロシア革命からの亡命者と、アメリカからの留学生がもたらす、ヨーロッパの東西、大西洋両岸を挟んでの文化の往来が、西洋音楽を掻き回し、思い掛けない活況を呈することに...
そんな、1920年代というパーティーへ!エリック・ル・サージュのピアノを中心に、腕利きたちが集ったミヨーの室内楽作品集(RCA RED SEAL/74321 801032)と、ローター・ツァグロセクの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏で、シュレーカー、シュルホフ、ヒンデミットの知られざるバレエを集めた"TANZ GROTESK"(DECCA/444 182-2)を聴く。
そんな、1920年代というパーティーへ!エリック・ル・サージュのピアノを中心に、腕利きたちが集ったミヨーの室内楽作品集(RCA RED SEAL/74321 801032)と、ローター・ツァグロセクの指揮、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の演奏で、シュレーカー、シュルホフ、ヒンデミットの知られざるバレエを集めた"TANZ GROTESK"(DECCA/444 182-2)を聴く。
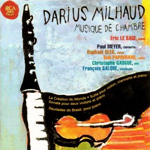
1920年代、パリで一世を風靡したフランス6人組。そのひとり、ミヨー(1892-1974)。この人の音楽性は、まさに1920年代の気分そのものだったと言える。リオでカーニヴァルに熱狂し、ニューヨークの喧騒に佇み、ラテンもジャズも取り込んで、ヤリ過ぎなくらいに、無邪気に、楽しい音楽をパリで繰り広げる!フランス音楽切ってのお祭り野郎。その底抜けの明るさは、フランス伝統の明朗さに裏打ちされながらも、どこかで、第1次大戦の傷を抱えた自棄っぱちにも感じられる。そんなミヨーの室内楽を取り上げるル・サージュ... ミヨーの代表作のひとつ、ジャズを取り入れたバレエ『世界の創造』のピアノ五重奏版(track.1-5)、ラテンに彩られた『ブラジルの郷愁』のピアノ独奏版(track.13-24)を軸に、この1920年代に生まれた2つの作品の前、第1次大戦、開戦の年、1914年に作曲された2つのヴァイオリンとピアノのためのソナタ(track.10-12)と、後となる、1936年に作曲されたヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲(track.6-9)を並べる。で、何と言っても室内楽という規模が効いている!お祭り野郎な響きは抑制され、フランスの作曲家らしいエスプリが随所からこぼれ出し、思い掛けず、素敵!特に、オリジナルであるオーケストラ版に聴き馴染んでいる『世界の創造』(track.1-5)!
アフリカからの視点(を担うのが、黒人文化に根差したジャズ、とのこと... )で、旧約聖書の天地創造を描き直すという、ミヨーらしい大胆なアイディアなのだけれど、それを、ピアノ五重奏という、ヨーロッパの伝統を象徴するような編成で奏でるパラドックス。で、いいのか?なんても思うのだけれど、これもまた作曲者自身によるアイディア... で、このパラドックスが大胆なのかもしれない。何より、そこから生まれるケミストリー!世界が創造されて行く厳かな始まりは、弦楽の落ち着いた響きが活きて、味わい深く、のっけから新鮮。やがて、楽しげなジャズが繰り出されると、ピアノ五重奏という親密な規模が、かえってジャズ・バンドの雰囲気をなぞらえて、魅惑的!オリジナルのワチャワチャした感覚が抑えられ、ジャズのいい雰囲気が引き立つからおもしろい。続く、ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲(track.6-9)、2つのヴァイオリンとピアノのためのソナタ(track.10-12)では、フランス音楽らしい流麗さにも彩られて、ミヨーの音楽の確かさを感じ、ヨーロピアンな心地良いひと時が訪れる。その後で、ル・サージュが弾く『ブラジルの郷愁』(track.13-24)が続くのだけれど、ウーン、ムーディー... けして過剰になることなく、さり気なくブラジルの表情をピアノで捉えて行くあたりは、クラシック離れしているかも... いや、お洒落で、粋で、お祭り野郎に走らないミヨーの姿が、洗練を感じさせ、惹き込まれる...
そんな、ミヨーの室内楽を聴かせてくれたル・サージュ。いや、ル・サージュのセンスの良さ、バランスの良さも大きいのかもしれない。とにかく、取り上げられる4つの作品の全てが、ナチュラルに奏でられ、スーっと耳に入って来る。元来、癖の強いミヨーの音楽のはずが、そういう、ある種のミヨーのはったりを弱め、作品ひとつひとつに籠められた音楽としての魅力を上手にすくい上げる。すくい上げることで強調される、ミヨーの音楽のフランス音楽としてエスプリ。伝統の崩壊を思い知らされるようなミヨーの存在だけれど、ジャズでも、ラテンでも、その音楽には「フランス」がしっかりと存在しているのだなと... そんなル・サージュの下に集った腕利きたち!ヴァイオリンのパパヴラミ、クラリネットのメイエなど、本当にゴージャスな面々が揃いつつ、しっかりとル・サージュの音楽性に共鳴して生まれる、極上のサウンド!いい具合に個性が抑えられて、「フランス」に焦点が絞られ生まれる魅惑!この薫り漂う雰囲気には、酔わずにいられない。
DARIUS MILHAUD ・ MUSIQUE DE CHAMBRE
■ ミヨー : ピアノと弦楽四重奏のための演奏会用組曲 『世界の創造』 Op.81a ****
■ ミヨー : ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲 Op.157b **
■ ミヨー : 2つのヴァイオリンとピアノのためのソナタ Op.15 **
■ ミヨー : ピアノのための舞踏組曲 『ブラジルの郷愁』 Op.67
エリック・ル・サージュ(ピアノ)
ポール・メイエ(クラリネット) *
テディ・パパヴラミ(ヴァイオリン) *
ラファエル・オレグ(ヴァイオリン) *
クリストフ・ゴーグ(ヴィオラ) *
フランソワ・サルク(チェロ) *
RCA RED SEAL/74321 801032
■ ミヨー : ピアノと弦楽四重奏のための演奏会用組曲 『世界の創造』 Op.81a ****
■ ミヨー : ヴァイオリン、クラリネットとピアノのための組曲 Op.157b **
■ ミヨー : 2つのヴァイオリンとピアノのためのソナタ Op.15 **
■ ミヨー : ピアノのための舞踏組曲 『ブラジルの郷愁』 Op.67
エリック・ル・サージュ(ピアノ)
ポール・メイエ(クラリネット) *
テディ・パパヴラミ(ヴァイオリン) *
ラファエル・オレグ(ヴァイオリン) *
クリストフ・ゴーグ(ヴィオラ) *
フランソワ・サルク(チェロ) *
RCA RED SEAL/74321 801032

さて、ミヨーのフランスから、ドイツ語圏の1920年代へと目向けるのだけれど、いやー、フランスとはまた違う独特なテイストが渦巻いている!で、そのドイツ語圏の1920年代の音楽を聴かせてくれるのが、1995年、第2次大戦後50年を機に、DECCAがナチスの迫害を受けた作曲家たちによる退廃芸術の烙印を押された作品を掘り起こしたプロジェクト、"ENTARTETE MUSIK"のシリーズから、知られざるバレエを取り上げるアルバム、"TANZ GROTESK"... ウィーンで学びドイツ語圏で活躍したユダヤ系、シュレーカー(1878-1934)による組曲『王女の誕生日』(track.1-6)に始まり、ユダヤ系チェコ人で、ドイツ語圏でも活躍したシュルホフ(1894-1934)のダンス・グロテスク『夢遊病者』(track.7-12)、ドイツ人ながらナチスと対立し、後にアメリカへと亡命したヒンデミット(1895-1963)のダンス・パントマイム『悪魔』(track.13-20)という3作品。戦後70年を過ぎてもなお、「知られざる」であって、極めつけのマニアック... それは、ナチスが退廃芸術の烙印を押し、葬ったからなのか?いやいやいや、1920年代ならではの新奇さ、ドイツならではのキッチュさが炸裂しているからだと思う。退廃芸術の烙印を押されてしまうほどのインパクトが、"TANZ GROTESK"には、間違いなくある。
そもそも、"TANZ GROTESK"、グロテスクなダンスなのである。その時点で凄い... しかし、最初に取り上げられるシュレーカーの『王女の誕生日』(track.1-6)は、拍子抜けするほどロマンティック。というのも、バレエそのものは、第1次大戦前、1908年に作曲(室内オーケストラ用... )されており、このアルバムで取り上げるのは、1923年にオーケストレーションし直された組曲版... ということで、世紀末の気分ムンムン。1920年代のパーティーの浮かれようの中で、この世紀末風の耽美なあたりは、ある意味、グロテスクだったかも?いや、そういう旧時代の残り香が、まだまだ漂っていたのも、1920年代の音楽の錯綜をより濃いものとしているのかもしれない。続く、1925年に作曲されたシュルホフの『夢遊病者』(track.7-12)は、シュルホフ芸術を象徴するような構成... ふんだんに盛り込まれたジャズに、ダダイスト、シュルホフが、とうとう音楽で"ダダ"を表現し切ったステップ(track.10)が聴き所!パーカッションのみで、飄々とリズムを刻むだけという、まさにダダイスティックさ!これは音楽なのだろうか?というリアクションが、"ダダ"として正解なのだよな... いや、キッチュでウケる!
そして、最後は、1922年に作曲されたヒンデミットの『悪魔』(track.13-20)。ヒンデミットの作風が、表現主義から新即物主義へとうつろう頃で、表現主義のマッドさと、新即物主義のドライでメカニカルな感覚が絶妙に重なり、ヘヴィーでクールな音楽を繰り出される。それは、無声映画を見るような、独特な雰囲気が立ち込め、悪魔の暗躍を緊迫感を以って描き出すようで、ミヨーのフランスの対極にあるテイスト... そんなテイストを生み出すのが、19世紀の音楽を主導したドイツが培って来た地力だろうか?伝統は失墜しても、ベースとなって、しっかりと機能しているのがドイツ語圏の1920年代の音楽の特徴か... だからこそ、グロテスクが引き立って来るというおもしろさ!伝統に裏打ちされた確かなグロテスクのダークな感覚が、たまらない。
という、"TANZ GROTESK"を繰り広げた、ツァグロセク、ゲヴァントハウス管。世紀末(シュレーカー)に、ジャズ(シュルホフ)に、表現主義+新即物主義のハイブリット(ヒンデミット)と、一筋縄では行かないドイツ語圏+チェコの1920年代を、丁寧に紐解くツァグロセク。丁寧でありながらも、切っ先鋭い時代の気分をしっかり捉えてもいて、刺激的。このあたりは、さすがの名門、ゲヴァントハウス管。マニアックな演目も、スパっと鋭利に捌き、飄々と堂に入った演奏を展開する。だからこそ、活きるグロテスク!ちょっと痺れてしまう音楽世界... で、ドイツは、やっぱり仄暗い... フランスの後だと余計に...
TANZ GROTESK ・ SCHREKER/SCHULHOFF/HINDEMITH
Zagrosek/Gewandhausorchester Leipzig
■ シュレーカー : 組曲 『王女の誕生日』
■ シュルホフ : ダンス・グロテスク 『夢遊病者』
■ ヒンデミット : ダンス・パントマイム 『悪魔』 Op.28 *
ローター・ツァグロセク/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
ヨーゼフ・クリストフ(ピアノ) *
DECCA/444 182-2
Zagrosek/Gewandhausorchester Leipzig
■ シュレーカー : 組曲 『王女の誕生日』
■ シュルホフ : ダンス・グロテスク 『夢遊病者』
■ ヒンデミット : ダンス・パントマイム 『悪魔』 Op.28 *
ローター・ツァグロセク/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団
ヨーゼフ・クリストフ(ピアノ) *
DECCA/444 182-2



コメント 0