まるで不条理劇?シェーンベルク、オペラ『モーゼとアロン』。 [before 2005]
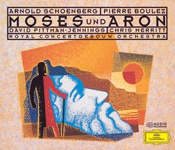
ファラオもファラオだけれど、そんなファラオに対するモーゼの執拗さも、かなりのものでして... もちろん、そこには神の意志があり... いや、神様は時として理不尽?ファラオに対する要求のみならず、旧約聖書にはそうした場面がいろいろある。となると、人間は神様にもてあそばれている印象を受けてしまう。しかし、神様云々に関わらず、思うように行かないのが人生であって、それを神様の視点から語ることは、腑に落ちるものもあったのだろう。ギリシア悲劇と共通する感覚を、そうしたあたりに見出す。が、ギリシア悲劇に対しての旧約聖書は、何だか不条理劇に思えることも... もちろん、ギリシア悲劇は文学であって、人の創作だから、ブラッシュ・アップされていて当然かもしれないが、ギリシア神話に至っても、何か、ストーリーに対して美意識のようなものを感じる。だからこそ、ギリシア神話は悲劇になり、多くの芸術にインスピレーションを与えたのだろう。そして、旧約聖書は... その不条理さが、妙にリアルに迫る?ギリシアの古典美にはない、現代を突き刺す生々しさがあるのかも...
さて、エジプトでのモーゼに続いて、紅海を渡ったモーゼたちのその後を見つめるオペラ... ピエール・ブーレーズの指揮、ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の演奏、ネーデルラント・オペラ合唱団のコーラス、デイヴィッド・ピットマン・ジェニングス(バリトン、)のモーゼによる、シェーンベルクのオペラ『モーゼとアロン』(Deutsche Grammophon/449 174-2)を聴く。
コジェルフのオラトリオの後に聴く、シェーンベルクのオペラというのは、衝撃的なくらいにビター... それはもう「晦渋」とすら言えるのかも... で、同じモーゼを主役に据えながら、こうも激烈にコントラストが付くかと慄いてしまう。もちろん、古典主義に対してのシェーンベルクの音楽ならば、そりゃ当然ではあるのだけれど、改めて音楽史の大きな流れから考える古典主義とシェーンベルクの距離には、面喰う(本当に同じジャンルなのだろうか?)。それをまた強調するように、凄い音楽を繰り広げる『モーゼとアロン』であって...
オラトリオなのにオペラ的なコジェルフとは裏腹に、オペラと銘打ちながらオペラ的なドラマティシズムを排した、12音技法による特殊な形を提示するシェーンベルク。12音技法を用いながらも、流麗さを表現できた、弟子、ベルクのオペラとは一線を画す。で、当初、カンタータとして構想されたとのことだが、納得させられる。出エジプトという大きな目標を成し遂げたヘブライの民が、シナイ山の麓の荒野に放り出されて惑う姿をそのまま描く音楽は、ドラマというよりはリポートか?そう言う点で、オラトリオにも思える。また、未完(第3幕は、台本のみが完成され、音楽はスケッチが残るのみ... )に終わったことも、その印象を強める気がする。ドラマとして完結していない状態が、旧約聖書を語るに留まっており、だからこそ、その宗教性が際立ち、旧約聖書を聖典としない者には晦渋なのかも... しかし、その晦渋さに、不条理劇を思わせる魅力を見出してしまうと、癖になる。
さて、ナチスの台頭が著しかった頃、ユダヤ系のシェーンベルクがアメリカへと亡命を余儀なくされる3年前、1930年、『モーゼとアロン』の作曲は始まった。そうした時代の空気をたっぷりと含んだ音楽には、何とも言えない不穏さが立ち込める。それでいて、シェーンベルクによる台本は鏡にも思える。人々の不安がアロンを担ぎ出し、偶像を掲げ、道を踏み外す... 全体主義へと陥る1930年代のドイツの状況が炙り出されるようで、何だかヒリヒリする。また、シュプレッヒゲザンクに近い形で語られるモーゼ役のセリフの無骨さ、神の意志を伝える人々を射抜くような実直さには、ドイツ語の響きも相俟って、ヒトラーのイメージとも重なるような... 人々は歌によって表現されるのに、モーゼだけがより直截に台詞を発する異様さ。それは、神々しくもあり、あるいは孤立にも見え、言いようの無い苦いものを感じる。第2次大戦の暗い記憶を抱える日本人だから、そう聴こえるのだろうか?掴みどころの無いような物語に、様々なメッセージが籠められるようで、深く考えさせられる。
そんな、『モーゼとアロン』で、何かと注目を集めるのが、狂乱の場(disc.2, track.11)。黄金の子牛の偶像を祀っての乱交!ヴィジュアルのセンセーショナルさの一方で、音楽は複雑さを極め、指揮者泣かせとも言われるのだけれど... そのモーゼの不在中に起こる退廃が描かれる第2幕、第3場(disc.2, track.4-11)の音楽は、それまでとは、幾分、響きがすっきりして、重苦しい空気は晴れるのか、いや、途端に音楽がキラキラとし出すからおもしろい。それはまるで、黄金の装飾を纏ったクリムトの絵画を見るような感覚かもしれない。シェーンベルクもまた世紀末のウィーンで青春を送った人物... 退廃にある種の輝かしさを持たせてしまうのは性?やっぱり、悪徳の方が魅惑的?そこにまた、旧約聖書の鋭い問い掛けがあるのかも...
で、この特殊なオペラを見事に捌き切るブーレーズ!それはさすがの指揮ぶりで、ロイヤル・コンセルトヘボウ管もしっかりと複雑な音楽を捉えて、圧巻。それでいて、鮮やかに群衆を描き出すネーデルラント・オペラ合唱団、ピットマン・ジェニングスのモーゼを筆頭に、熱い歌を聴かせる歌手陣と、何とも言えずエモーショナル!12音技法によるオペラという、音楽的感情を殺すようなイメージを、思い掛けなく裏切り、これによって、ドラマがどっと重みを増し、そうして生まれる迫力が凄い。いや、これが、20世紀の重みだろうか?ブーレーズにしてブーレーズを越えた重量感に驚きつつ、惹き込まれる。
ARNOLD SCHOENBERG: MOSES UND ARON
PIERRE BOULEZ
■ シェーンベルク : オペラ 『モーゼとアロン』
モーゼ : デイヴィッド・ピットマン・ジェニングス(語り)
アロン : クリス・メリット(テノール)
少女 : ガブリエーレ・フォンターナ(ソプラノ)
病める女 : イヴォンヌ・ナーフ(アルト)
若い男/裸の若者 : ジョン・グラハム・ホール(テノール)
若者 : ペール・リンドスゴク(バリトン)
もうひとりの男 : ジークフリート・ローレンツ(バリトン)
エフライムの徒 : ミヒャエル・デヴリン(バリトン)
祭司 : ラースロー・ボルガール(バス)、他
ネーデルラント・オペラ合唱団、ツァンス少年合唱団、ウォーテルラント音楽学校生
ピエール・ブーレーズ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
Deutsche Grammophon/449 174-2
PIERRE BOULEZ
■ シェーンベルク : オペラ 『モーゼとアロン』
モーゼ : デイヴィッド・ピットマン・ジェニングス(語り)
アロン : クリス・メリット(テノール)
少女 : ガブリエーレ・フォンターナ(ソプラノ)
病める女 : イヴォンヌ・ナーフ(アルト)
若い男/裸の若者 : ジョン・グラハム・ホール(テノール)
若者 : ペール・リンドスゴク(バリトン)
もうひとりの男 : ジークフリート・ローレンツ(バリトン)
エフライムの徒 : ミヒャエル・デヴリン(バリトン)
祭司 : ラースロー・ボルガール(バス)、他
ネーデルラント・オペラ合唱団、ツァンス少年合唱団、ウォーテルラント音楽学校生
ピエール・ブーレーズ/ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
Deutsche Grammophon/449 174-2



コメント 0