ふたりのシュミット。 [2007]
久々に新ウィーン楽派の音楽を聴いて、いろいろ考える...
新ウィーン楽派による12音技法の発明が、その後の音楽を一変させた!と、何となく把握している近代音楽史なのだけれど、そういう教科書的な捉え方というのは、実際とは違うニュアンスを含むのかもしれない。新ウィーン楽派の面々というのは、新しいことを始めた一方で、その新しいものに対して、優柔不断だったようにも感じるし。その新しいもので、音楽史を大きく前進させたことは間違いだろうが、革命的なグループというのは、往々にして少数派であったりする。新ウィーン楽派に限って言えば、時代(その当時... )に理解されないと、卑屈になるようなところもあったりで、どこか情けない風情でもあり。
となれば、新ウィーン楽派を取り巻いていた当時の音楽シーンというか、モード?空気感?みたいなものは、どうだったのだろう?と、気になる。そういう周辺を含んでこそ音楽史だと思うし... そこで、シェーンベルク(1874-1951)と同世代の、新ウィーン楽派でない作曲家を聴いてみる。ティエリー・フィッシャー率いる、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団による、フロラン・シュミットのバレエ『サロメの悲劇』(hyperion/CDA 67599)と、カルロ・グランテのピアノで、ファビオ・ルイジが率いた、MDR交響楽団による、フランツ・シュミットの左手のためのピアノ協奏曲集(Querstand/VKJK 0611)。2007年にリリースされた2つのアルバムを聴き直す。
新ウィーン楽派による12音技法の発明が、その後の音楽を一変させた!と、何となく把握している近代音楽史なのだけれど、そういう教科書的な捉え方というのは、実際とは違うニュアンスを含むのかもしれない。新ウィーン楽派の面々というのは、新しいことを始めた一方で、その新しいものに対して、優柔不断だったようにも感じるし。その新しいもので、音楽史を大きく前進させたことは間違いだろうが、革命的なグループというのは、往々にして少数派であったりする。新ウィーン楽派に限って言えば、時代(その当時... )に理解されないと、卑屈になるようなところもあったりで、どこか情けない風情でもあり。
となれば、新ウィーン楽派を取り巻いていた当時の音楽シーンというか、モード?空気感?みたいなものは、どうだったのだろう?と、気になる。そういう周辺を含んでこそ音楽史だと思うし... そこで、シェーンベルク(1874-1951)と同世代の、新ウィーン楽派でない作曲家を聴いてみる。ティエリー・フィッシャー率いる、BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団による、フロラン・シュミットのバレエ『サロメの悲劇』(hyperion/CDA 67599)と、カルロ・グランテのピアノで、ファビオ・ルイジが率いた、MDR交響楽団による、フランツ・シュミットの左手のためのピアノ協奏曲集(Querstand/VKJK 0611)。2007年にリリースされた2つのアルバムを聴き直す。
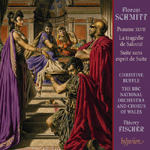
フロラン・シュミット(1870-1958)。フランスのシュミット(ドイツ系なのだけれど... )。
ここのところ、立て続けに、その代表作、バレエ『サロメの悲劇』がリリースされていて、気になる。密かに、人気作品ということになりつつあるのか?で、2007年にリリースされた、フィッシャー+BBCウェールズ・ナショナル管のアルバムを引っ張り出して来て、聴き直す。のだが、『サロメ... 』だけでないこのアルバム... 実は、『サロメ』以上にインパクトがあったのが、1曲目、詩篇、第47番(track.1-4)。
その名の通り、旧約聖書を歌うわけだが、大規模なコーラスが、アグレッシヴに濃厚に歌い上げる!初めて聴いた時は、何とも分かり易い迫力に、多少、面喰うというか、そうしたあたりに、チープな印象を持ったのだが、改めて聴くと、また違った感覚で向き合えるような。近代音楽が動き出した時代、1904年の作品だが、『春の祭典』の初演(1913)はまだ先で、12音技法の発明(1920年代初頭)はまだまだ先... そういう段階で、これは、十分にモダンだったのでは?とも感じる。印象主義にエンジンを取り付けてパワフルにし、ストラヴィンスキーのバーバリスムが遠くに見え始めたような。過渡期の音楽かもしれない、しかし、その瞬間、やれることをやり切った音楽、あらゆる意味でマキシマム!で、おもしろいのは、どこか古き良きハリウッド大作の映画音楽のような、そんなテイストでもあり。伝統のクラシックの枠を越えたダイナミックさと、ダイナミズムの後で、たっぷりとロマンティックにも酔い痴れ... そのキャッチーさが、実は、21世紀の今、かなりツボなのかも。どこか懐かしい、ノスタルジック・モダン?ノスタルジックだけれど、やたらエモーショナルで。フィナーレなんて、パイプ・オルガンは鳴るは、ここぞとばかりに盛り上げて。その元気の良さが、何だか魅力的。
さて、バレエ『サロメの悲劇』(track.10-15)だが... 謎めく前奏曲(track.10)に始まり、フランスの伝統に則って、スパイスとしてのエキゾティシズムも効かせ、ソプラノ・ソロと、女声コーラスのスキャットが印象的な海上の誘惑(track.13)に、煌びやかなオーケストラ・サウンドが、大胆にリズムを刻む稲妻の踊り(track.14)と、じわりじわり盛り上がる。さらに、ストラヴィンスキー調のバーバリスティックさものぞかせる恐怖の踊り(track.15)が続き、フィナーレ。『春の祭典』に比べれば、刺激は欠けるが、伝統と近代の二兎を追って紡がれるフロランならではのサウンドは、ある種の、いいとこどり。また、ティエリー・フィッシャーの絶妙なさじ加減と、BBCウェールズ・ナショナル管の煌びやかな演奏が、そのあたりを強調し、きっちり楽しませてくれる。詩篇、第47番も含め、これぞオーケストラ!という充実感が詰まった1枚だ。
SCHMITT PSAUME XLVII ・ LA TRAGÉDIE DE SALOMÉ
BBC NATIONAL ORCHESTRA AND CHORUS OF WALES / THIERRY FISCHER
■ フロラン・シュミット : 詩篇 第47番 Op.38 ***
■ フロラン・シュミット : 組曲 「形ばかりの組曲」 Op.89
■ フロラン・シュミット : バレエ 『サロメの悲劇』 Op.50 **
クリスティーン・ブッフル(ソプラノ) *
ジェニファー・ウォーカー(ソプラノ) *
BBC ウェールズ・ナショナル合唱団 *
チャールズ・ハンフリーズ(オルガン) *
ティエリー・フィッシャー/BBC ウェールズ・ナショナル管弦楽団
hyperion/CDA 67599
BBC NATIONAL ORCHESTRA AND CHORUS OF WALES / THIERRY FISCHER
■ フロラン・シュミット : 詩篇 第47番 Op.38 ***
■ フロラン・シュミット : 組曲 「形ばかりの組曲」 Op.89
■ フロラン・シュミット : バレエ 『サロメの悲劇』 Op.50 **
クリスティーン・ブッフル(ソプラノ) *
ジェニファー・ウォーカー(ソプラノ) *
BBC ウェールズ・ナショナル合唱団 *
チャールズ・ハンフリーズ(オルガン) *
ティエリー・フィッシャー/BBC ウェールズ・ナショナル管弦楽団
hyperion/CDA 67599

フランツ・シュミット(1874-1939)。オーストリアのシュミット(生まれはスロヴァキア... )。
フランツというと、オラトリオ『7つの封印の書』がすぐに思い出されるのだが、ここで聴くのは、第1次世界大戦で右手を失ったピアニスト、パウル・ヴィトゲンシュタインのために作曲された2曲。ベートーヴェンの主題による協奏的変奏曲(track.1-7)と、ピアノ協奏曲(track.8-10)。なのだが... プロコフィエフの4番のピアノ協奏曲、ブリテンのディヴァージョンズ、リヒャルト・シュトラウスのパレルゴン、そして何よりラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲と、ヴィトゲンシュタインをめぐる作品の録音は、左手だけで演奏するというイレギュラーさの一方で、けして珍しくはない。が、フランツの作品となると、極めて珍しい。で、どんな作品かと、興味津々で初めて聴いた時の印象は、あまりに薄かった... が、今、改めて聴いてみると、けしてそんなことはないから不思議。
前半、ベートーヴェンの主題による協奏的変奏曲... 思いの外、美しい曲で、驚かされる。オーストリアのシュミットの、独墺系、正統派クラシックの伝統を受け継ぐ端正な音楽が、ベートーヴェンとよく共鳴し、ヴァイオリン・ソナタ「春」からのテーマが、見事に、魅力的に変奏されて、左手だけだからと聴き劣りすること無く。また、左手だけというあたりが、ピアノのサウンドを引き締め、よりくっきりとその存在が浮かび上がるようでもあり。そもそも、片手で変奏してゆくなど、ちょっと、思いも付かないわけだが、そのハンディを見事に活かして美しい音楽を紡ぎ出すのだから、フランツのセンスに驚かされる。それでいて、"ruhig fließend"(track.3)のような、極めつけの甘さ(まさに、リヒャルト・シュトラウス!)で、ロマンティシズムが溢れ返ったりすると、つい感激してしまう。多少、安易でも、美しさに弱いと言うか、抗し難い美しさで、ちょっとメロメロに。もちろん、そればかりでなく、ひとつひとつの変奏がそれぞれに豊かな表情を見せ、終わり方もチャーミング。思わぬ再発見に... やっぱり、CDは寝かすといい。
そして、後半、ピアノ協奏曲(track.8-10)。ロマンティックな場所に留まりながらも、独自の進化を遂げたフランツならではのサウンドが印象的。概ねロマンティックだけれど、それまでの伝統を捏ねている内に、ロマンティックの外へとうっかりはみ出してしまうような瞬間があって、それらがスパイスにもなり。モダニスティック・ロマンティック?爛熟期を過ぎたロマン主義を、律儀に紡ぎ続けた価値は間違いなくあったと思う。そんなフランツ作品に精力的に挑んだファビオ・ルイジ... 4つの交響曲に、オラトリオ『7つの封印の書』も録音しての、左手のためのピアノ協奏曲集だっただけに、MDR響を駆使し、ロマンティシズムのジューシーさと、新ウィーン楽派とは別経路の進化、伝統の深化の先を丁寧に捉えて、見事な演奏を聴かせてくれる。カルロ・グランテによる左手だけでのピアノも、片手であるということを忘れさせるタッチで、フランツ作品の魅力をきっちり楽しませてくれる。
FRANZ SCHMIDT | CONCERTANTE VARIATIONEN | KONZERT ES-DUR
■ フランツ・シュミット : 協奏的変奏曲 〔ベートーヴェンの主題によるピアノ(左手)とオーケストラのための〕
■ フランツ・シュミット : ピアノ協奏曲 変ホ長調 〔左手のための〕
カルロ・グランテ(ピアノ)
ファビオ・ルイジ/MDR 交響楽団
Querstand/VKJK 0611
■ フランツ・シュミット : 協奏的変奏曲 〔ベートーヴェンの主題によるピアノ(左手)とオーケストラのための〕
■ フランツ・シュミット : ピアノ協奏曲 変ホ長調 〔左手のための〕
カルロ・グランテ(ピアノ)
ファビオ・ルイジ/MDR 交響楽団
Querstand/VKJK 0611



コメント 0